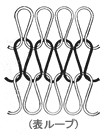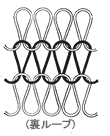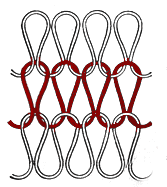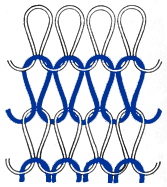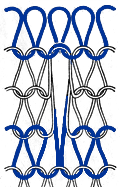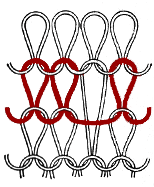繊維の種類・織物・ニット生地の特徴・用語の繊維サーチ
SENI-SEARCH.JP
ニットには緯編(よこあみ)と経編(たてあみ)があり、この類別によって編成方法も異なる。
手編みの原理を利用して機械化した緯編と織物織布の理論を適応した経編とは同一の編機で編むことはできない。
並列した編み針に糸を90度の方向から供給し、ループを作らせ、縦に連綴させる緯編に対し、経編では、並列した編み針に対した編針に対し、糸を同方向から供与し、ループ編成をさせたのち、隣接するループに次々とつづらせていく。ここでは編針の使用組み合わせ方法、ゲージにも著しい相違がみられる。 緯編:平編、ゴム編、パール編の3元組織。
経編:開き目と閉じ目(シングル・デンビー編)を原組織として、その他さまざまな種類がある。主要編機は、トリコット編機、ミラニーズ編機、ラッシェル編機である。
透孔編、透かし目編、フィレット編、ニードル・ループ目移しともいう。透かし目を有するメリヤス編の総称。原組織の1つのループを隣のループに移して重なったループとしたもので、目移しやタック作用によってレースのような透かし目を編成する。1本の糸と1本の針で編んだ連続ルー王の鎖編は、レース編の1種。 編地の特徴:多種多様な柄の透かし目があることで、著しい美観を示す。べら針、ひげ針のいずれによっても編成されるが、とにも目移し針を用いる。 編機:円形橫編機、平型橫編機、スパイラル編など。 編生地:メッシュ 用途:カーテン、レース、靴下(メッシュ柄靴下)、家庭用服飾品など |
|
|
フル・カーディガン編、ポルカ・リブ(polka rib)ともいう。 橫編機の両針床で交互にタック編したゴム編変化組織。ゴム編の両面にタック編を応用したもので、四ツ山橫で、4個のカムのうち、斜対象位置にある2個のカムをタック位置にして編成する。 編地の特徴:ウェール方向に畝がはしり、厚地で保湿性に優れていることである。適度な弾力性をもち、伸縮性はまりない。 編機:各種畦編編機、フライス編機、円形ゴム編機 編生地:フライス生地、ポルカ・リブなどと呼称され、テレコ生地もこの種に属す。 用途:靴下、シャツ、セータなど |
|
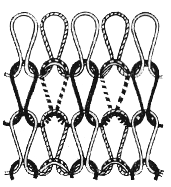 |
ハーフ・カーディガン編ともいう。 平型橫編機の片側の下げカムの1つをタック位置にして編んだ片面タックのゴム編変形組織。つまりゴム編の片面にタック編を応用したもので、分厚な生地を売る場合に利用される。 編地の特徴:両畦編同様、ウェール方向に畝が走り、厚手の弾力性に富み、伸縮性があまりないことである。 編機:平型橫編機、フライス編機 編生地:フライス生地、テレコ生地 用途:靴下、シャツ、セータ、ジャージーなど |
| シンカ・ループ目移しともいう。 特殊な針を用いて進化・ループ(sinker loop)を拡大し、それを次のコースで隣の針に引っ掛けて編んだ透孔組織。つまり編目を移動してレース目を作る編編成方法で、ある部分のシンカ・ループを次のループの編成前に編針にかけるわけである。 編地の特徴:レース目で外観が美しく、しかも比較的厚地で通気性に富むことである。 編機:アイレット編機 編生地:アイレット生地、バスケット生地 用途:肌着、セータ、家庭用服飾品など |
|
|
ペレリン編などを用いて、編地に小穴をあけた組織。 平編、又はゴム編地にペレリン編を応用して編成し、フライス生地の裏目に互い違いに穴があいたものとなっている。 編地の特徴:透かし目模様。所謂アイレット孔があることで、平編又はゴム編にペレリン編をかみしたそれぞれの個性を持っている。 編機:円形アイレット編機、模様アイレット編機などのゴム編機で、べらは針が用いられる。 編生地:アイレット生地、模様アイレット生地(菱形、筋柄などのアイレット孔を持つ)、プレーン・アイレット生地(平編にペレリン編を応用したもの)、リブ・アイレット生地(ゴム編にペレリン編を応用したもの) 用途:男物半袖丸首、婦人物スリマー、シュミューズなど。 |
|
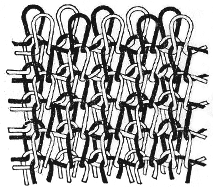 |
スムース編(circular interlock knitting)、両面スムース編、インターロック(interlock)、
メリディアン(meridian)、ダブル・リブ(double rib)、二重ゴム編(double rib)ともいう。 2つのゴム編を腹合わせにしたゴム編変化組織。フライス生地(ゴム編)のヴェールの間に、いま1つのウェールが介在する組織である。基本的には、長短2種類のバットを持った有りで編成し、2口の糸で1コースを完成するもので、第1の糸を上針の奇数番目のものと下針の偶数番目の物とによって編む。この変化組織には、2×2ゴム編を重ねたエイト・ロック(eight lock)がある。また3組以上のゴム編を組み合わせたり(多衝程両面)、タック、ミス、ニットを組み合わせ応用することにより各種の変化組織(針抜き、タックを併用したもの、パール編、浮き編、レース編、添え糸逆転編、パイル浮かし添え糸編、ゴム糸挿入など)をうることが出来る。 編機:インターロック編機、スムース編機といわれる円型両面編機を使用。 編生地:裏表ともに一見平編のように見えるなめらかさを持ち、同一構成であるため、緻密、重厚、堅牢である。適度に伸縮性を押させており、弾力性に富み、捲れることがなく安定している。 |
ダブル・ジャージー、ダブル・ニットともいう。 両面編の変化組織。 両面編のバット針は、2種類であるが、これを3種類以上用いて編成したもので、ダブル・ニードル・マシンによって両面出合いをさせた複合組織。このほかゴム編出合いの物がある。3段両面編、クロス・ミス・インターロック、ロイアル・インターロック、ブーレ、モック・ミラノ・リブ、シングル・ピケ、テキシービケ、ピン・タック、タック・リップル、ポンテ・デ・ローマなどがあり、その編成可能性はほとんど無限に近い。 編地の特徴:各種各様であるが、一般に、裁断、縫製に適し、伸縮性が少なく、腰のある耳捲れしない生地となっている。 編機:多衝程両面編機、ダブル・ニット編機(フライス機、両面機)が使用される。 編生地:ダブル・ジャージーと呼ばれるが、その種類は多種多様。 用途:外衣用ジャージー |
|
|
ダブル・ニットともいう。 ゴム編の変形組織で、ダブル・ニードル・マシンによって、3種類以上のバットを用いて編成した複合組織。なお、ダブル・ジャージには、ゴム編出合いによるものの他に、両面出合いによるものがある。 ミラノ・リブ、ダブル・ピケ、リリーフ、ハニー・カム、スペシャル・ダブル・ピケ、オーバー・ニットなどがある。なおジャカード・ジャージーと家荒れるものは、ダイアルの2本の針とジャカード方式で選別された針とで編成する柄入りゴム編の1種である。 編地の特徴:裁断、縫製に適し、伸縮性が少なく、腰があり耳捲れしない。 編機:ダブル・ニット編機(フライス機、両面機) 編生地:ダブル・ジャージー 用途:外衣用ジャージー |
|
| ショッキング、ラッキングともいう。 橫編機で、片畦または両畦編を編みながら、片側の針床を1針間ずつ左右に数段振って編んだ組織。つまり片畦、両畦編の応用組織で、基本の網目をそのままにして、キャリジの往復毎に後部針床を全部針床に対し1針間だけ移動させ、これを繰り返し、直線状で平行なウェールを千鳥状のウェールに変えたもの。またタックと振り子を併用して、斜め状の編地を作ることもある。キャリジ1往復毎に1回振るものを1回振りというが、両畦編にカムを配置して数コース半回振りをし、同コース1回振りを追加し、組み合わせ編成すると、ジグザグとなった編地の矢振り編となる。千鳥状、またはジグザグのウェールがはしっており、比較的厚地で装飾性に富むことが編地の特徴。 編機:平型橫編機を中心に、両頭橫編機、パイル編機を用いる。 編生地:両頭生地(無地編および優れた各種柄編がある) 用途:実用外衣、セータ、肌着用生地、手袋、靴下、帽子、ジョールなど |
|
| 編針を適当な位置で抜いて編んだ組織。ゴム編の応用組織で、片側編針だけを針抜きにするものと、両側の針床で針抜きをするものがあり、針抜きにしたところはループが形成されず編地は縦縞となる。各組織と併用して柄編の変化を出し、2×2ゴム編から1×1ゴム編に変換する場合のように組織変換するときにも用いられる。 編地の特徴: 縦縞生地であり、また深くひだをとることが出来る。 編機:フライス編、円型ゴム編機、スムース機 編生地:針抜き柄 用途:外衣用柄生地、靴下、下着、肌着、セータ |
|
| パイル編、プラシ編、ビロード編ともいう。 編地の面にリング状にパイルを出した組織。厚地の生地をうるために、表面ないしは裏面、さらには両面を立毛(pile)で覆うもので、地糸にパイル系を添え編し、特別装置でパイル系のシンカ・ループを拡大し、パイル・ループを編成する。この場合ゴム編、平編を応用する。仕上げでは、ループのまま放置すると、切って羽毛にするものがある。 編地の特徴:厚地で保温性に富み柔らかく、パイルの為、外観がビロード状を示すことである。 編機:両面編機、両面パイル編機、フライス編機、シール編機、フライス・シール編機、橫編機、台丸機など 編生地:シール、立毛メリヤス生地、パイル生地、ハイパイル生地 用途:防寒用肌着、イミテーション毛皮、外衣、帽子、インテリア製品など |
|
| フリース編(fleecy stitch)、プラシ編(plush stitch)ともいう。 裏糸、地糸あるいはこれに中糸を加えて編成する組織で、地糸を平編にし、裏糸を浮き編にして、裏面にパイルを出し、仕上げ加工で起毛するものである。つまり裏糸をパイル状に編み込んで浮かせた組織である。裏糸に太い糸を用い起毛しないでシングル・ジャージーを作ることが多い。編地は厚地で保温性に富み、丈夫で実用性に優れる。 編機:吊編機が中心で、他に台丸機、トンプキン機を使用する。 編生地:裏毛メリヤス 用途:実用外衣、防寒用肌着、下着 |
|
| プレーティングともいう。 2種類の糸を用いて、1方の糸が他を覆うように編んだ組織。平編、ゴム編の組織と同じであるが、柄編や補強をするときに応用され、地編糸に他の糸を添え編し、表と裏とに異なった糸を出すと美しいが、実用性に重点が置かれ、きわめて丈夫である。 編機:円型平編機、円型ゴム編機などがあり、生地にはリップル柄生地などがある。 用途:靴下、セータ、ジャージーなどの要補強部分 |
|
| 刺繍編、エンブロイダリングともいう。 地組織は、普通に編み、別の糸で地組織の中に縦メリヤス目を同時に編み込んで、縞や模様を編成するもの。編地は、縞や模様をうる刺繍編であるため美しい外観を示し、各種柄に恵まれる。 編機:円型靴下編機 編生地:ボックスネック柄、ボス柄、捲付柄、ラップ柄生地 用途:靴下 |
|
| 橫編機で、2種の針を使用して1方の針が平編をし、他の針がタック編をし、鹿の子柄、亀甲柄を表したもの。つまり高バット針と低バット針にタック編をさせ、蕾形やパイナップル状のふくらみを変化柄組織である。なおラーベン・パイル編は、パイルの柄編をしたもので、ラーベン編の変形組織。編地は、鹿の子柄や亀甲柄を鮮明に表し、もっとも美しい緯編の1つとなっている。 編機:橫柄編機であるラーベン編機 編生地:鹿の子生地、ラーベン生地、特殊ラーベン生地(幾何学模様、亀甲柄、縦縞柄、網代柄) 用途:肌着、セータ、ジャージーなど |
|
| なわ編ともいう。 平編の若干のウェールを交互に移しかえして、なわ状に編んだ組織。 編地は、なわ状のウェールがはしったものとなる。 編機:橫編機 |
|
| 種々の色彩のダイヤモンド形の模様を編み込んだ柄編。 編地の特徴:スポーティな柄合いを見せる。 編生地:ダイヤモンド形のほか山柄、稲妻柄。 用途:靴下、セータ、手袋 |
■編物の種類:
緯編生地 ![]() 平編変形組織
平編変形組織 ![]() リブ編変形組織
リブ編変形組織 ![]() 両面編変形組織
両面編変形組織 ![]() パール編変形組織
パール編変形組織
経編生地 ![]() トリコット(別ページ)
トリコット(別ページ) ![]() ラッセル(別ページ)
ラッセル(別ページ)
テキスタイル・織物名称説明はこちら![]()
生地の柄の種類(ストライプ・チェックなど)の説明はこちら![]()
繊維業界関連用語集(日本語・英語・意味)はこちら![]()
日本の織物産地マップはこちら![]()
参考書/引用文献(Reference)
灘 五郎(1967).新しいニットの知識, 長江書房
灘 五郎(1967).新しいニットの知識, 長江書房

 平編(Plain Stitch )
平編(Plain Stitch )